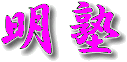教務部長からの一言

気づかせる教育
問題の意味を理解する力、問題の言葉から考えられる知識を頭の引き出しから出す力、引き出した知識を組み合わせて問題を解く力。この3つの力を付けるのが「気づかせる教育」です。
「この問題が出来るか」が大切なのではなく、そのような問題が出たときに、自分で考えを作って解けるかが大切です。
~生徒のみなさんへ~
テストのときには、お父さんもお母さんも友達も塾の先生も、何の役にも立ちません。頼りになるのは自分だけです。難しい問題があったとき、努力をしてきて考える力のある自分と、あまり勉強をしていなくて考える力のない自分と、どっちが頼りになりますか?困ったときに頼りになる自分になりましょう。
過去ログ
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
7月25日(木)更新
夏休みが始まりました。学校から出された宿題をどんどん進めている子やプールに行って楽しかった話をしてくれる子、高校生では、夏休みの始めと終わりの1週間は学校の夏期講習があって、お盆にはバイトの人手が足りないからいつもよりたくさんシフトを入れられて、完全オフの日が少ないと言っている子など、それぞれにそれぞれの夏休みがあります。ニュースでは、いろんな所に旅行に行く家族などが紹介されていますが、実際生徒たちに聞いてみると、何泊も旅行をする人は少なくて、「おばあちゃんちに行くくらいかな」という子がほとんどです。生徒を見ていると、「勉強はしっかりやりや!でも楽しいこともたくさんあるといいね。」と思います。
7月17日(水)更新
生徒たちから部活の話を聞くと、「あー…」と思ってしまうことがあります。けがをした生徒がいます。まだ十分に治っていないのに、「出れるか?」と顧問の先生に聞かれます。その先生が、少し厳しい先生なら、生徒は「まだ出れません」とは言いにくいものです。本当はまだ痛いのに「出れます」と言ってしまって、試合に出てまた痛めるということになります。勉強という場での先生と生徒の関係と、スポーツという場での関係は、力関係が少し違うのですが、それに気づかずに指導をしている先生は少なくありません。熱中症が心配される季節になりました。正しい知識を持っている指導者ならいいのですが、そうではない場合もあります。しんどいとき、それをわかってもらえないなら、「わざと倒れなさい」と生徒たちに言っています。最後に自分の命を守れるのは自分なので。
7月11日(木)更新
「自分がやりたいこと」と「やらなければならないこと」を書き出してみてください。例えば3つずつ書いたとしたら、それに優先順位の番号を書いてみましょう。一般的に年齢が低いほど自分がやりたいことを優先して、責任を考えるような年齢になるほどやらなければならないことを優先します。今の自分はどっちですか。小学2年生と高校3年生が同じ感覚で優先順位をつけていてはいけません。自分がつけた優先順位を客観的に見てください。本当にこれでいいのかと。…究極の優先順位に「トリアージ」というものがあります。大規模な災害で重傷者がたくさんいるときに医療者が治療の優先順位をつけるものです。重大なことになればなるほど、感情に左右されない優先順位の判断が必要になります。考えてみましょう。
7月4日(木)更新
先日、以前担当していた生徒が会いに来てくれました。小さい時から役者になりたいと思っていた生徒で、大学に入学直後でしたが東京でオーディションを受け、大学は休学ということにして養成学校に入りました。それから1年後の去年、芸能事務所からのオファーがあり、その事務所に所属する役者になりました。それから1年がたち、今の様子を話しに来てくれました。初舞台で準主役の役をもらって舞台に立てたこと、大きな企業のポスターのモデルに採用されて、それは全国の駅などで使われたことなど、順調に進んでいることを話してくれました。彼は役者になるために特別なことをしていたわけではありません。地元の中学校から公立の高校に入って、ハンドボール部で部活をしていたくらいです。あるとしたら、小さいころから空手をずっと続けていたことくらいです。そんな彼が、役者希望の子がたくさんいる東京で、なぜ業界の人の目に留まり成功しようとしているかというと、人を尊重し、自分に誠実であることだと思っています。人としての資質です。そして、ずっといろいろな視点で考えて生きてきた力だと思います。
6月26日(水)更新
「教える」という言葉の意味を、広辞苑で調べてみました。いくつか意味が書いてある中に、「知識を与えて理解させる」とありました。私がどうしていまさら調べたかというと、世の中の「教える」ということが、「知識を与える」になっているように思ったからです。「知識は与えたから、あと理解するかどうかは個人の努力に任せる」みたいな考え方の「教える」です。「教える」という仕事は、「理解させる」まで責任をもつことです。世の中の「教育」という現場の中に、「知識を与える」で終わってしまっていることがたくさんあると感じて嘆いています。そして、そのことで一番困っているのは生徒たちです。
6月19日(水)更新
私が担当している高校生の中の2校が、今、北海道に研修旅行に行っています。2校とも農業体験が中心の旅行です。約2日間、畑か牧場で作業をします。私は子供のころ福島県の田舎で田んぼや畑の手伝いをして、牛のえさの世話もしていました。土のにおい、わらのにおい、草を焼くにおい。私にとってはどれもいい匂いですが、はたして現代の高校生にはどうなのか、いきなり北海道の農場で、どんなことになっているのか少し心配もしています。生徒たちも行く前から、どんなことになるのか不安そうでした。来週にはその生徒たちの授業があります。何を話してくれるのか、今から楽しみにしています。
6月12日(水)更新
私が高校生の時、それぞれの教科のノートというのは作っていませんでした。今のようにノート提出というようなことがなかったので、ノートの有る無しや、書く内容は生徒に任されていました。私は、自分に必要なことだけを書けばいいと考えていたので、わざわざ各教科のノートを作らず、ルーズリーフ1つに全教科の必要なことを書いて済ませていました。もちろん、教科ごとにノートを作っている人もいて、自分のために必要なことを書いていました。最終的に勉強が出来るようになることが目的なので、その手段としてのノートは、提出物でもなく自由でした。今は、ノート提出というのが課題になっていて、きれいに完璧に仕上がっていることを求められています。当時の私が今存在していたら、最低の評価を受けることになります。評価されるためにノートを書いている生徒を見ると、考えさせられます。
5月29日(水)更新
「ルートの計算なんて、実際使わへんし」とか「どうせ外国なんて行かないし」とか耳にします。数学や英語が出来なくてもいい理由、やらなくてもいい理由のようです。でもこれはうそです。こんな理由のためにやらないわけではありません。本当の理由は「やりたくないから」「面倒だから」です。本当の自分と向き合いたくないから、何かのせいにしてごまかしています。今はこんなふうにごまかしていても成り立つかもしれません。でも、受験のときには「やりたくないからやらなかった。」なんて何の役にも立ちません。やりたくなくてもやる自分になっていなければなりません。だとしたら、いつからそういう自分に変わる気ですか。「そのときになったら」と思った人!「そのとき」では遅すぎます。
5月23日(木)更新
勉強が難しくてわからなくなったり、友達関係でややこしいことになって、どうしていいかわからなくなったり、その結果、やる気が出なくなって何もしたくなくなるってことがあります。一度立ち直っても、同じようなことが繰り返されると、立ち直ってもどうせまたダメになるし…と思って、立ち直る気力さえなくなっていきます。そんな時に思ってほしいことがあります。それは、「それでも自分は生きていく」ってことです。どれだけ気力を失っても、明日は来るし、明日も自分は生きていきます。何かを食べるだろうし、いくらかでも動きます。もしそのとき、一人暮らしとかで自分しかいなかったら、自分を助けるのは自分しかいません。ですから、自分を助けられる自分になりましょう。
5月15日(水)更新
危険予知という能力はとても大切です。スマホを見ながら、歩いたり自転車に乗ったり。倒れたら大変だというものを高く積み上げていたり。SNSに個人情報を気にせず載せたり。先の結果を考えないでやってしまう。こうしたらどうなるということを事前に考えて防ぐ能力は誰にでも必要なものです。それは勉強も同じです。学校の授業を聞かなかったり、宿題をしなかったりしたらどうなるのか?「危険」というわけではありませんが、先の自分を考えて今するべきことを判断するという点では同じです。「あー、あのときスマホを見ながら…なんてしてなかったら」「あー、あのときもっとちゃんと勉強していたら」こんなことを、後になって言わないようにしましょう。
5月8日(水)更新
生徒に「学校で今なにやってる?」と聞くことがよくありますが、それに対する反応はいろいろです。「なんやったっけ?」という子もいれば、教科書やノートを出して、「ここ」という子もいます。「なんやったっけ?」と言う生徒は授業を聞いていなかったことになります。理由を聞くと、なるほどと思うこともありますが、それでも、今何をやっているかわからないのがいいわけはありません。どんな状況だろうと、今やるべきことは何か、自分にとっていいことは何かを考える必要があります。だれかのせい、何かのせいでやらない気持ちはわかります。でも、そのせいでできなくなって傷つくのは自分です。将来の自分を傷つけないように、今やれることをやりましょう。
5月1日(水)更新
この春から新しい生徒を何名か担当しています。私が「どんな生徒かな?」と思うのと同じように、生徒たちも「どんな先生かな?」と思っています。怖い先生だったらどうしよう…とか。とても心配してそうな生徒には、「先生は絶対に怒らない」という話をします。「わからない問題があったとき、怒ったらわかるようになると思う?絶対にないよね。わかりやすく説明をするからわかるわけで、怒ったからわかるなんてことは絶対にないよ。だから先生は怒らない。」と言うとホッとした笑顔を見せてくれます。実際、緊張した状態で説明を聞いても十分に理解はしてもらえません。リラックスして聞くから頭に入るし理解もできます。「この先生には何を聞いても大丈夫」という安心感をあげることも私の仕事です。
4月25日(水)更新
今日はたこ焼きを作ろうと思ったら、材料を用意しますね。たこ、小麦粉、卵、鰹節などなど。それがなければ買いに行くことになります。たこ焼きを作るためにはその材料が必要なことは、だれだって分かっています。勉強も同じで、計算をしたり文章を書いたりするためには、それをするために必要な材料がいります。ほんの短い文章でも「これがいい」「これでいい」のように、「が」と「で」の違いを知っておくことが、書くための材料になります。たこ焼きなら、あれがないこれがないと材料の不足がすぐわかるし、ないと困るとみんな思います。ところが勉強となると材料が不足しているのに、「ま、いいか」とごまかします。おいしいたこ焼きを作るのと同じように材料をそろえましょう。
4月17日(水)更新
昨日、中2の生徒が、学校でわからなかったという英語のプリントを持ってきました。塾の授業でやってもらうと、ほとんどヒントなんて言っていないのに出来ていきました。「なんで学校で出来なかったのに塾ではできるんやろう?」と言うので、ちょっとした実験をしました。まず、「簡単な計算問題を言うよ。答えてな。」と言ってから、「4+3は」と言うと「7」と即答してくれました。次に、「もう1問いくよ。」と言ってから、「5+3は」と言い、間髪いれず私が「答えて!答えて!早く答えて!」とまくしたてると、「8」と答えるのに3秒くらいかかりました。驚いたような顔をしている生徒にどうだったか聞くと、「一瞬頭が真っ白になった。」と言いました。余裕がない緊張した状況ではこんなことになるという実験です。生徒は、「緊張するとやばいってよくわかった。」と言っていました。
4月10日(水)更新
もし「洗濯は、洗濯板でしなさい。」と言われたらどうしますか?だれだって不便になるのは嫌ですね。昭和のころ、デパートは夕方6時が閉店でした。テレビは夜中の12時ごろ放送終了で、電話は固定電話しかありませんでした。ところが今は、24時間営業も珍しくなく、夜中でもアニメなど放送していて、電話は無料通話がし放題です。おまけにスマホが出来てから、24時間楽しいことがありすぎです。すべては、大人の「経済」という都合で出来たものです。こんなに楽しいことや便利なことを子供たちに与えておいて、それをうまく使っていくことを個人の努力に頼っている世の中はずるいなと思っています。そういうずるい大人の一人として、せめて、あまり楽しくない勉強を少しでも楽しいと感じてもらえるように、授業をしています。
4月3日(水)更新
小学校の教科書が新しくなります。指導要領が変わるからではなく、デジタル教科書の完全化を進めるための改訂です。デジタル教科書とは、これまでの紙の教科書をそのままタブレットで見ることができるようにしたもので、教科書は紙とタブレットの2つが存在するということになります。紙の教科書のほとんどすべてのページにはQRコードがついて、音声や画像や動画を利用した学習ができるようになります。宿題のタブレット化もさらに進むことになるので、親にとっては、何が宿題として出ているのか把握しにくくなります。タブレットにタッチペンで書くのと、紙に鉛筆やシャープペンシルで書くのとでは手の感覚が違うので、そういうことで学習にどんな影響が出てくるのか、興味をもっておかないといけません。
3月27日(水)更新
私の名前は「よしお」です。ですから子どもの時、私は母親から「よっちゃん」と呼ばれていました。そしてその母親から私が言われていたのは「よっちゃんはだいじょぶだ!」です。「勉強しなさい」ではなくて、「だいじょぶだ!」です。何の根拠があるのかはさっぱりわかりませんが、気がついたらそう言われていました。高校生までずっとそう言われ続けた私は、大丈夫じゃない自分でいるわけにはいかなくて、必死で勉強しました。中2の時には、実力テストの日の朝、ストレスがかかりすぎて胃がけいれんしてしまって救急車で運ばれてしまうくらい必死でした。「勉強しなさい」「勉強してるの?」は疑う心からで、「だいじょぶだ!」は信じる心から起こる言葉です。信じられてしまったらやるしかありません。
3月20日(水)更新
高校入試が終わりました。受験生たちはほっとしていると思います。受験勉強に疲れてしばらく休憩と思っている人が多い中で、すでに高校に向けて始動している生徒もいます。高校に入った後のその先に目標を持っている生徒です。高校合格をゴールだと思えば「休憩」となりますが、その先に高いレベルの目標があれば、じっとしていられなくなります。とても分かりやすいことですが、人は目標をもてば動くということです。「将来」などという大きな目標ではなくても、「こうなりたい」と思えば、そうなるように動けます。もうすぐ4月です。みんながステップアップします。それぞれに目標を作りましょう。そして動き出しましょう。
3月13日(水)更新
入試や学年末テストが終わりました。中学受験、高校受験、大学受験、中学と高校の学年末テストです。たくさんの生徒と関わってきて感じるのは、「先を想像する力がどれだけあるかで、今することが変わる」ということです。「今を生きる」とか「今を大切にする」という言葉があります。この言葉を都合よく解釈すると「今がよければそれでいい」というようになってしまいます。「今困っていないからこれでいい。」“今”をこんな風に思ってしまうと、どんどん自分を甘やかしていくことになります。そして先の自分が困ることになります。先のことを考えての今なら、今がよければ…とはなりません。先を想像して準備をしておくことが自分を大切にすることです。今がよければ…という考えは、先の自分を傷つけています。
3月7日(木)更新
世の中のいろんな出来事がネットで取り上げられ、いろんな人がコメントを書いています。そのほとんどは、自分の中の「普通」とか「正しさ」を基準にして書かれています。そして、そのせいで傷ついている人がいます。本当は、みんな自分が知らない経験や人生を送っています。ですから、そんなに簡単に「正しい」とか「違う」とか言ってはだめなんです。その人のことを知らないうちに決めつけてはいけないんです。・・・もうすぐ年度替わりです。新しいだれかと出会うときです。新しい環境を楽しみにしている人もいますが、不安に思っている人もいます。もし新しいだれかに「自分とは違うな」と思うことがあったとしても、すぐにいいとか悪いとか思わないで、「あーそうなんだあ」という気持ちになってもらえたらと思っています。
2月28日(水)更新
先週の日曜日、美術系の高校に進んだ生徒の卒展があると聞いて、見に行ってきました。中3まで担当していた生徒なので、会うのは3年ぶりです。作品も楽しみですが、生徒に会えることがもっと楽しみで行きました。3年間をどう過ごしていたか、中3の時と変わっていたらそれはそれで、中3の時のままならそれも、どちらでもその子が3年間を過ごした姿です。会場に着くと、その子は友達といっしょにいました。友達からは「おじいちゃんですか?」と聞かれ、「そうです。」とふざけて答えました。美術担当の先生もいて少し話をしました。卒展の作品がどんな風にして出来上がったのかなど聞いていたら、中3のままの姿が重なって来て、感性は変わっていないことを嬉しく思いました。美術大学に進学なので、また楽しみが増えました。
2月21日(水)更新
先日、JAXAが「H3」ロケット2号機の打ち上げに成功しました。去年の3月に1号機の打ち上げに失敗していたので、今度はどうかと興味を持っていました。1号機の失敗は2段目のロケットエンジンに着火しなかったという失敗で、2段目エンジンに着火の信号を送ったところまでは確認されていました。その信号を受信できなかった原因について、考えられるあらゆることをひとつひとつ実験し検証し、解明するという作業を続けて今回の成功につなげました。すべての関係者の努力が2号機の成功につながっています。そうです。努力は目標につながっていないと意味がありません。中学2年生が行きたい高校の話をしてくれました。私は「じゃあ、これからしていくことがその高校につながることかどうかが判断のポイントになるね。」と言いました。行動が目標につながっていれば達成できます。
2月14日(水)更新
今日は多くの私立高校の合格発表です。全員の合格を願っています。そして、明日と明後日は公立高校の前期選抜です。それぞれがベストを尽くしてくれることを祈っています。入試の直前はみんな不安になったり緊張したりします。みんなそうです。余裕で合格しそうな子だって緊張はします。不安になったり緊張したりする自分に不安にならなくても大丈夫です。みんなそうだから。入試の会場に行くと、まわりの子たちがみんな賢そうに見えます。それもみんな同じです。別にまわりの子が賢いかどうかなんてわからないのに勝手にそう思ってしまいます。だから、そう思ってしまう自分に不安にならなくても大丈夫です。みんなそうだから。入試のときに自分に出来ることは、「問題をよく読み、そのことについて考えて、答えを書く」ということです。ですから、そのことにだけ集中して下さい。わからない問題があることだって想定内です。動揺なんてしないで、出来ることをやりましょう。
2月7日(水)更新
「ゆったし!」・・・「そんなん聞いてへんし!」日常のどこかでありそうなことです。このふたりは、本当に言ったし、本当に聞いていないんだと思います。言う方の声が小さかったり早口だったり、聞く方が何かに夢中で上の空だったり。この場面には、大切なことが欠けています。言葉は言うためのものではなくて伝えるためのものだということ。確かに言った言葉でも、それが伝わっていなければ意味がありません。また、どう伝わるかを考えることも大切なことです。「言う」という行為の主体は自分です。「どう言おうか、なんて言おうか」と考えているときは自分中心です。もしかしたら言葉がとがっていて、相手を傷つけるような伝わり方をするかもしれません。言うことが大事なんじゃなくて、どう伝わるかが大事。それがコミュニケーションだと思います。
1月31日(水)更新
昨日、ある生徒の授業で少し時間が余ったので、クイズを出しました。問題です。国語辞典が2冊本棚の右端に立ててあります。1冊の厚さは5㎝で、表紙の厚さが表も裏も5mmあります。今1時間に1㎝の深さで本を食べながら進む虫がいたとして、この虫が右端の1冊目の表表紙からその左側の2冊目の裏表紙まで食べて穴をあけるのにかかる時間は何時間でしょう?―国語辞典が2冊並んでいるのを想像して、1冊目の表表紙から2冊目の裏表紙まで10㎝と考えれば答えは10時間となりますが、正解は1時間です。ポイントは「国語辞典」です。縦書きの国語の本は、立てたとき左側が表、右側が裏になります。ですから、国語の本を2冊並べて立てた1冊目の表表紙から2冊目の裏表紙まで、表と裏は隣り合うので虫が食べる距離は表紙の厚さ2つ分の1㎝なので答えは1時間になります。ホワイトボードに本と虫の絵をかいて、おもしろおかしく表現すると、楽しんでやってくれました。
1月24日(水)更新
受験生の中には入試に面接がある生徒がいます。先日面接練習をした生徒は、言うべきことを一生懸命覚えてきて、志望動機を言ってくれました。がんばって練習したことは分かるのですが、良くはありません。志望動機ですから、その学校に対する意欲を話すことになりますが、一生懸命覚えてきたことを話す生徒の口から出てくる言葉はまるでセリフのようでした。いきいきと意欲を語る語感がありません。面接は会話です。活字にはない「声」という情報が加わります。「できます。」という言葉も、低い声で語尾を下げて言えば、本当にできるのか疑わしい感じに伝わります。その逆に、少し高い声で語尾を上げて言えば、自信がありそうな「できます。」になります。面接で大切なのは、覚えたことを間違えずに言うことではなくて、面接官に自分のことを教えてあげるという感覚です。
1月17日(水)更新
日曜日、みやこめっせに行ってきました。以前担当していた生徒が大学院生になっていて、制作した作品が展示されているということで見に行ってきました。本人とも時間を合わせていたので、5年ぶりの再会で3時間も話をしました。小学生から高3まで担当していて、当時から物事を深く考える生徒でしたが、そのころと変わらないでいてくれました。いろいろな人との関わりの中で感じてきたことなどを話してくれました。先生はどう考えますか?というので私なりの考え方も話しました。やりたいことがたくさんあって、どれにしたらいいか決められない生徒でしたが、そこも同じで、卒業後のことも何にするか経験している最中で、まだ決められないと言っていました。大学に入ってからしてきたことを写真で見せてくれて、その子の5年間がよくわかりました。とても嬉しかった出来事でした。
1月10日(水)更新
人は結果がわからないことに対して不安になります。熱が出たとき、どこまで上がるんだろうという不安。テストなら、できるだろうかという不安。面接なら、ちゃんと言えるだろうかという不安。病気のように自分ではどうすることもできない不安は、気持ちの持ち方を変えるしかありませんが、テストや面接のような自分で何とかできる不安なら何とかしましょう。結果がわからないから不安になるのなら、「これは出来る」「これは言える」というように結果がわかることを増やしていけばいいだけです。勉強をして出来るようになる。声に出して言えるようになる。出来た分だけ不安は減ります。不安な時、優しい言葉は心を癒してくれますが、不安を消してはくれません。不安を消せるのは、「できる」という自分です。